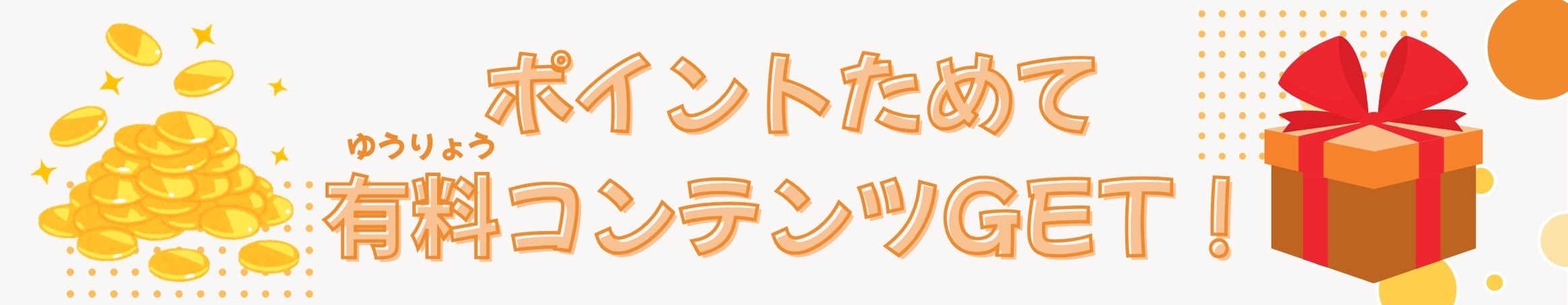ビジネスでは客観的なデータとして「数字」が使われますが、その数字の見せ方や文化的な背景によって、受ける印象は大きく変わります。特にインドネシア、ベトナム、ミャンマーなど、自国の通貨の桁数が多い国の方が日本で生活すると、日本円の金額が数字の見た目だけで実際よりも安く感じてしまう「桁の錯覚」に陥りがちです。数字の裏にある意味や単位を正確に捉える習慣をつけなければ、ビジネスでも私生活でも大きな損をする可能性があります。
【注意したい日本語表現Ⅲ】数字の捉え方の意義
ビジネスシーンにおいて、数字を正しく読み解くことは、「事実(ファクト)に基づいて正しい判断をする」ために不可欠です。特に桁数の違う国でビジネスをする際、例えばインドネシアルピアやベトナムドンに慣れていると「10,000(一万)」という数字は非常に小さな額に感じます。しかし日本の「10,000円」は決して小さな額ではありません。この感覚のズレが、コスト計算のミスや契約での誤解を招きます。数字を「記号」ではなく「価値」として認識することが重要です。
ビジネスで特に注意したい数字の表現
通貨の桁(ゼロの数)の違い
インドネシアの「10万ルピア」、ベトナムの「20万ドン」、ミャンマーの「1万チャット」のように、日常的に大きな桁の数字を扱うことに慣れていると、日本での「1万円(10,000円)」という値札を見た時、感覚的に「安い」と錯覚しやすい危険があります。
注意点:
(錯覚)「ランチで 1,500 か。自国の 1,500 ならすごく安いな。」
(現実)「待てよ、1,500『円』だ。自国の通貨に換算すると(例えばベトナムドンなら)約25万ドンだ。決して安くない。」
(注意)「このジャケットは 20,000(二万)か。桁が少ないから買おう。」
(現実)「20,000『円』だ。(インドネシアルピアなら)約200万ルピアもする。よく考えよう。」
「〜円から」という最低価格表示
広告やメニューでよく見る「〜から」という表現です。これは最も安いオプションの価格であり、自分が欲しいものがその値段とは限りません。
注意点:
(広告)「引越し料金 10,000円〜」
(現実)実際に見積もると、荷物の量や距離で 5万円になることもある。
(広告)「月額980円から使い放題」
(現実)それは最低プランであり、快適な速度そくどや機能を求めると月額4,000円のプランが必要だったりする。
「平均」という言葉のワナ
「平均」は、データ全体の真ん中を示すとは限りません。一部の非常に大きい(または小さい)数字に引っ張られて、実態とかけ離れることがあります。
注意点:
(データ)「社員の平均年収は800万円です。」
(実態)ほとんどの社員は400万円で、社長だけが5億円もらっている場合でも、平均は高く出てしまう。中央値(真ん中の順位の人)を見ることが重要。
「最大〜%オフ」という割引表現
セールなどで目にする「最大」という言葉は、ほとんどの商品がそれに当てはまらないことを示唆しています。
注意点:
(広告)「店内の商品、最大70%オフ!」
(実態)実際には、ごく一部の売れ残りだけが70%オフで、人気の商品はすべて10%オフだったりする。
単位のない数字(グラフなど)
会議の資料などで、グラフや表の単位(「円」なのか「件」なのか「人」なのか)を省略すると、大きな誤解を生みます。特に桁の感覚が違うと危険です。
注意点:
(資料)「今期の売上:1,000」(← 1,000円? 1,000万円? 1,000億円?)
(推奨)「今期の売上:1,000万円」または「単位:百万円」と必ず明記する。
(資料)「コスト:50」
(確認)「この50とは、50万円ですか、それとも50万ドン(約3,000円)ですか?」と必ず確認する。